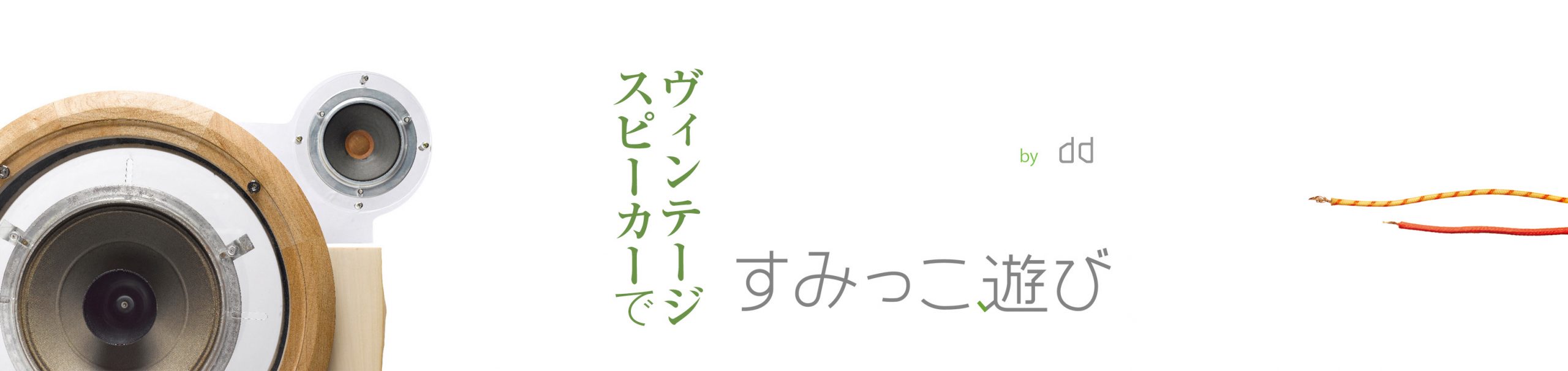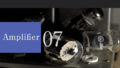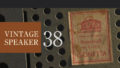レコードが聴ける、トランジスタ無帰還アンプの配線をお願いしている工房からの帰り道、素敵なカフェに連れて行ってもらいました。Rola 8吋ユニットを後面開放でモノラル音楽を流す、山の中にある小さなカフェ。ヴィンテージ・スピーカーの世界に入る時イメージしていた音が、そこにはありました。その音は、何本ヴィンテージ・ユニットを購入しても聴くことができないでいた幻の音。それが、このカフェ「あがりだん」に流れています。初めて好きになった人が、そのままの姿で目の前に立っているみたいな感じです。数少ないレコードは「ベンチャーズ」と「スプートニクス」それに「ブレンダリー」。あとは加山雄三の「ブラック・サンド・ビーチ」と全てドーナツ盤。これを国産のステレオで何度も楽しんだ、祖父の家の応接間が懐かしい。ターンテーブルがスプリングで浮かされ、確かリバーブも付いていて、それも好きでした。東芝製だったか・・薄い記憶。
SCHLZのKSP215や、Tru-Sonic、それにいつも聴いているPhilipsなど、どれもモノラルの味付け。「Philipsは、音量を上げるとすぐビビル」と店主。・・確かに苦労させられた。ずっと聴きたかったユニットの音まで聴けて、なんとも嬉しい時間。しばらく悩んでいたフェーダーも置いてありノイマン製でした。その中でも特に気になったのがCDプレーヤーです。ゲーム機のCD機構を組み込んだソレは、かなりグッドなデザインで、ああ欲しいと思わされ印象的でした。なんでも流通量が多いゲーム機のパーツを使うことで、後のメンテナンスも安心という納得の構造。考え方もグッドですね。
そんな美味なオーデイオですが、奥の部屋にあるIsophon製の小さなISONETTAは、特に年代物の酒のような味がする。楕円のユニットは、小さなサイズなのに、なんとも深く醸成された音を奏でます。楕円スピーカーは、今の平面バッフルでは使いにくく、未だ試したことがない別世界。もちろんアンプもこれに合った仕様でしょう。とにかく優しい音は、シトロエンにも似た癒しです。原音再生だとかステージの音が欲しい、などと考えたこともなく、ただガサついた心を保湿するクリームが欲しいと考える時、この音質は特効薬です。単に、このスピーカーを入手しても、再生環境が違うので、多分求めている音は出ないでしょう。難しいな。
「あがりだん」の音は、ボヤけた音ではありません。低域から高域まで、何気なくスッと出ていますが、輪郭を強調しないで実を存在させる世界観です。輪郭を強調すると、楽器が見えてきたりしますが、そうではなく血が流れ魂が宿る感じの音だと気付かされます。音楽の本質・・。15歳の頃、これを本当に感じていたのか??
カフェには、音を吸収する素材が溢れています。襖だったり畳だったり、自分の生活の中には存在しないアイテムばかり。そこから考えなければ、出しえない音。どう考えても到達することができそうにない音世界。
家にいるネコを観察していると、極小さな音に反応し、ジッとその方向を凝視することが多いようです。まず聴覚が反応して、方向をキャッチすると、そちらを見て視覚情報を得ようとします。感覚はどうも耳の方が先のようです。音楽に集中するとき、目を瞑りますね。目からの情報が余計だからです。目からの刺激入力には余計な経路があってそれがノイズになってしまう。多分、その多くは言葉的思考。そもそも表現は、言葉で表せない世界を描くもので、絵も音楽も同じです。言葉は、視覚と聴覚が合わさる場にあり、言葉の領域を超えてくる表現は、それを言葉で表現しようとするには無理があります。もちろん言葉を操る表現者は、その壁を越えようとするでしょう。そのことは別のこととして考えます。抽象画を理解できない、と言う話は、ここに主たる原因があります。
「あがりだん」にある音は、視覚と聴覚が微妙にブレンドして、なぜか視覚が気になりません。むしろ視覚効果が音に良い感じで影響しています。だから目を瞑る必要がありません。もちろんのように、CDプレーヤやターンテーブル、そして後面開放の箱のデザインだったりの視覚情報は溢れていますが、それが音楽と一緒になってしまう。オーナーのセンスが、この絶妙バランスを作り出しています。達人ですね。